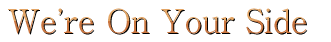Black Box -ブラックボックス-
山口敬之氏からレイプ被害に遭ったジャーナリストの伊藤詩織さん。
その詩織さんが自身の身に起きたことを詳しく書き綴った本が
去年の10月に文藝春秋から出版された。
新聞の広告欄を見て、この本のことを知った時すぐに読みたいと思い、
購入を決意したのだが、それよりも先に支援者の方などからこの本の
差し入れがあった。「方など」としたのは、この本の差し入れが一冊
二冊ではなかったからだ。それほど周りの人達は、この本は俺にとって
読むべき本だと判断したのだろう。実際に読んでみて、俺自身もこの本を
読んでおいてよかったと思った。
そう思えるだけの内容が、この本には書かれてある。
「we’re on your side」の活動を始めてから、性犯罪に関心を持つように
なり、それに関する書籍も読むようになった。
だが、性犯罪に遭った被害者の初動対応に関する知識についてはまだまだ
欠如していたと、この本を読み気づかされた。
またそれと同時に性暴力被害者に対する社会の配慮が欠如していることも
知った。
『 この時の私は、予約外でピルをもらえただけでも、感謝すべきだったかもしれない。
しかし、身も心も最大のダメージを受けている時、自力で適切な病院を探さなければならない
困難は、計り知れないものがあった。
その後、他の検査や相談したいと思い、ネットで調べて、性暴力被害者を支援するNPOに
電話すると、「面接に来てもらえますか?」と言われた。どこの病院に行って
何の検査をすればいいのかを教えてほしいと言ったが、
話を直接聞いてからではないと、情報提供はできないと言われた。
この電話をするまでに、被害に遭った人は一体どれほどの気力を振り絞っているか。
その場所まで出かけて行く気力や体力は、あの時の私には残されていなかった。
そうしている間にも、証拠保全に必要な血液検査やDNA採取を行える大事な時間は、
どんどん過ぎ去っていた。当時の私には、想像もできなかった。
この事実をどこかで知っていたら、と後悔している。』
『 絶望のどん底で、不安を胸に一杯抱えて警察の門をくぐった日のことを、今でも忘れない。
受付カウンターへ行くと、他に待合者がいる前で、事情を説明しなければならなかった。
簡単に事情を説明し、「女性の方をお願いします」と言うと、カウンターでさらに
いろいろ聞かれた。うまく伝わらないので「強姦の被害に遭いました」と言うしかなかった。
もう少し配慮が欲しいと思った。』
『 捜査の進展に伴い、事件の経緯を確認することが必要だ、と言われたのはこの頃だった。
「再現」と呼ばれるこの作業は、事件現場で行われることも多い。文字通り、
事件が起こった際の状況を再現し、写真に撮るのが目的だ。
この時は現場で行われず、高輪署の最上階にある、柔道場のようなところで行われた。
フロア一面に青いマットが敷き詰めてあり、壁には道着のようなものが並んでかかっていた。
多くの警察官がここで訓練して来たのだろう、少将汗臭い部屋だった。
男性捜査員たちの居並ぶ柔道場で、人形を相手にレイプの状況を再現させられるのだ。
「それではそこに寝てください」
と言われ、彼らに囲まれながら青いマットの上に仰向けになった。
一人の捜査官が私の上に人型の大きな人形を乗せた。
「こんな感じ?」
「もう少しこうですかね?」
と言いながら人形を動かす。フラッシュが光り、シャッターが押され始めたところで、
こわばらせていた心のスイッチを完全にオフにした。
同じ日であっただろうか。
捜査員に、「処女ですか?答えづらいかもしれませんが」と聞かれた。
他の捜査員からも以前から何度も聞かれたいたことだった。
私は繰り返されるこの異様な質問に対し、
ついに「それが事件と何の関係があるんですか?」と聞いた。
が、「どうしても聞かなければいけないことなんです」と言うだけだった。
この質問は、話をした捜査員全員から聞かれた。が、この時に聞かれるまで、
私は「何の関係があるのか」なんて問い返すことはできなかった。
ひたすら質問に答えるのが精一杯だった。
性犯罪の被害者が、このような屈辱に耐えなければならないとしたら、
それは捜査のシステム、そして教育に問題があるはずだ。
ロイターの同僚にこの話をしたところ、「それはセカンドレイプだ」と、
さっそく取材を始めた。これは警察での体験で一番苦痛を伴うことだったが、
この時は友人のKの同席がなぜか許されなかった。
一階の待合室で、この作業が終わるのを待っていてくれた。
彼女が近くにいてくれたら、少しは楽だっただろう。』
『 レイプの届け出件数が多いスウェーデンの実態を知るために、
私はストックホルム南総合病院にあるレイプ救急センターを訪れた。
ここは、三百六十五日二十四時間体制でレイプ被害者を受け入れている。
一つの入口は待合室を通らず、
誰とも顔を合せずに受付にたどり着けるようになっている。
内部はプライバシーが保てるように細かく仕切られていて、
入院はできないが、横になって休めるスペースがある。
また、レイプキットによる検査は遭ってから十日まで可能で、
その結果は六ヶ月間保管される。
被害者は、まずはこのレイプ救急センターで検査や治療、カウンセリングを受け、
一連の処置が終わった後に、警察へ届けを出すかどうか考えることができる。
もちろん、裁判に必要な証言などを得るには、裁判は早いに越したことはないが、
事件直後には、心身ともにダメージを受けているため、裁判に大変な負担がかかる。
この制度のおかげで事件に遭った人は、すぐに警察に行かなかった自分を責めたり、
どうしてすぐに警察に届け出なかったのかと周囲から責められたり、
これでは何もできないと当局から突き放されたりしなくて済む。』
気づかされたこととは別に改めて驚いたこともある。それはこの箇所だ。
『 山口氏の帰国に合わせ、成田空港で逮捕する、という連絡が入ったのは、
六月四日、ドイツに滞在中のことだった。
「逮捕する」という電話の言葉は、おかしな夢の中で聞いているような気がして、
まったく現実味を感じることができなかった。
「八日の月曜日にアメリカから帰国します。
入国してきたところを空港で逮捕する事になりました」
A氏は、落ち着きを見せながらも、やや興奮気味な声で話した。
逮捕後の取り調べに備えて、私も至急帰国するように、という連絡だった。
私はこの知らせを聞いて、喜ぶべきだったのだろう。
しかし、喜びなんていう感情は一切なかった。電話を切った途端、
体のすべての感覚が抜け落ちるようだった。
これから何が待ち受けているであろう。
相手から、彼の周囲から予想される攻撃を想像すると、どっと疲れを感じた。
少しずつ自分の生活を取り戻しつつあったところで、
またこの事件に引き戻された。
しかし、気持ちを立て直さなければならない。
事実が明らかになる時が来たのだ。
私は仕事を調整し、帰国できるチケットを探し始めた。
A氏はこれまで、「疑わしきは罰せず」と繰り返し私に言った。
「疑わしいだけで証拠が無ければ、罪には問えないんですよ」と。
それが、裁判所から逮捕状請求への許可が出るところまで、
証拠や証言が集まったのだから、大変心強いのは事実だった。
この電話から四日後、逮捕予定の当日に、A氏から連絡が来た。
もちろん逮捕の連絡だろうと思い、電話に出ると、
A氏はとても暗い声で私の名前を呼んだ。
「伊藤さん、実は、逮捕できませんでした。
逮捕の準備はできておりました。私は行く気でした、
しかし、その寸前で待ったがかかりました。
後任が決まるまでは私の上司の◯◯に連絡して下さい」
驚きと落胆と、そしてどこかに「やはり」という気持ちがあった。
質問が次から次へと沸き上がった。
なぜ今さら?何かがおかしい。
「検察が逮捕状の請求を認め、裁判所が許可したんですよね?
一度決めた事を何故そんな簡単に覆せるのですか?」
すると、驚くべき答えが返ってきた。
「ストップを掛けたのは警視庁のトップです」
そんなはずが無い。なぜ、事件の司令塔である検察の決めた動きを、
捜査機関の警察が止めることができるのだろうか?
「そんなことってあるんですか?警察が止めるなんて?」
するとA氏は、
「稀にあるケースですね。本当に稀です」
とにかく質問をくり返す私に対し、
「この件に関しては新しい担当者がまた説明するので。
それから私の電話番号は変わるかもしれませんが、
帰国された際は、きちんとお会いしてお話ししたいと思っています」
携帯電話の番号が変わる?A氏はどうなるのだろうか?
「Aさんは大丈夫なんですか?」
「クビになるような事はしていないので、大丈夫だと思います」
後は、A氏はひたすら謝り、私が何を聞いても、
「自分の力不足という事で勘弁して下さい」と言うだけだった。
「納得が出来ません」
今まで私は、何度かA氏に、
「そこまで捜査に口を出すなら自分でやってください、
警察なんていらないでしょ?」
と言われ、それからは警察に頼んだのだから、
絶対的な信頼をして協力をしようという姿勢を見せてきた。
そうしなければ、やる気を失われ、とり合ってもらえなくなると
身をもって感じたからだ。
しかし、ここまできたらもう、そんなことはどうでもよくなった。
「全然納得がいきません」
と私が繰り返すと、A氏は「私もです」と言った。それでもA氏は、
自分の目で山口氏を確認しようと、
目の前を通過するところを見届けたという。
何をしても無駄なのだという無力感と、
もう当局で信頼できる人はいないだろうという孤独感と恐怖。
自分の小ささが悔しかった。
今までの思い、疲れが吹き出るかのように涙が次から次へと流れ落ちた。
よく聞くと、A氏は逮捕が止められた理由について、
何も聞かされていないのだという。
それでは新しく担当になる人も同じなのでは?と言うと、
「そうだと思う」という返事だった。
A氏はこの二ヶ月間、ものすごく多くの時間を割いて
この事件について調べ上げ、私の主張と上からのプレッシャーに挟まれながらも、
最後まで頑張ってくれた。今さら誰が代わりになるというのだろう?
また振り出しに戻り、新しい捜査員に同じ話を何度もすることになるのだろうか。
お互いに言い争うこともあったが、A氏は懸命に捜査を続けてくれていた。
その人が担当を外れることは、逮捕が取り止めになったことと同じくらい、
私にとってショックだった。
彼は電話で最後にもう一度、
「力不足でごめんなさい」
と言った。私の口からは、
「本当にありがとうございました。お疲れ様でした。
これからもお体に気をつけて」
という以上の言葉が出なかった。
また、この事件のせいでA氏の仕事に影響を与えたことをお詫びして、
電話を切った。
一被害者、一捜査員という立場で今まで相当ぶつかり合ったが、
戦友と突然別れるような寂しい気持ちになった。
言葉にできないあらゆる感情と共に、涙が溢れた。
体の力が抜け、ベルリンの住宅街の道で一人途方にくれた。
本当にすべての道を塞がれてしまったのかもしれない。
私のような小さな人間には、もうこの目に見えない力に
立ち向かうことすら許されないのだ、と感じた。
警視庁上層部の判断。わかっていたことはそれだけで、これからも一捜査員、
一被害者が真相を知ることはできないのだと思った。
何か他のルートで調べる方法は無いのか。
「どこに聞けばいいのだろう」そんな考えがぐるぐる頭を回った。
私はすぐに、泊まっていたドイツの友人宅に戻り、キッチンから電話をかけた。
当時この事件を担当していたM検事に、話を聞きたかったのだ。
M検事あてに電話をかけると、「M検事はこの県から外れた」と電話に出た人は言った。
この人もだ。逮捕のストップがかかった当日に、この件を担当していたA氏も検事も、
誰もいなくなった』
警視庁だけではなく、検察にまでもここまで露骨な圧力をかけられるものなのかと
驚愕した。
また、この高輪署の捜査員だったA氏。
『 それから二日後、四月十一日に、再び原宿署で会ったのは、
この事件を担当してくれる高輪署の捜査員、A氏だった。
ここでまた、最初から事件の説明をした。A氏の応対は、原宿署の捜査員より、
ずっとハードだった。
「一週間経っちゃったの。厳しいね」
いきなりこう言った。そして、
「よくある話だし、事件として捜査するのは難しですよ」
と続けた。やっとの思いで警察を訪ね、
スタートラインに立てたと思っていた私にとって、
それはあまりに残酷な言葉だった。
私はこの事件を「よくある話」と聞いてゾッとし、
そんなに簡単に処理される話なのかと呆然とした。
「こういう事件は刑事事件として難しい。
直後の精液の採取やDNA検査ができていないので、
証拠も揃わなくて、かなり厳しい」
と繰り返すA氏に対し、
「ホテルがわかっているのだから、防犯カメラだけでも調べて下さい。
映像の保存期間が過ぎてしまう前に行って下さい」
と私は懇願した。この話を聞いた友人たちはみな怒り、警察への不信感を持った』
というこの記述を読んでいたので、A氏に対してどこか懐疑的な目を持ちながら俺は
この本も読み進めていたのだが、この箇所を読んだ時、その見方は変わった。
『 ある夜、知らない番号からの電話が入った。
誰かわからず緊張し、一瞬出ることをためらったが、取材先の人だったらと思い、
意を決して電話に出ると、それはA氏からの連絡であった。
高輪署から異動になったため、番号が新しくなったという。
山口氏を逮捕できなかったあの日以降、A氏の声を聞くのは初めてだった。
A氏は私に連絡することを、組織の人間として悩んだはずだ。
しかし、「私がヘマをしたのではないので、それだけはお伝えしたかった」と言った。
A氏は懸命に捜査をしてくれたし、何よりもプロだった。
自分のミスで山口氏の逮捕ができなかったと思われることが、苦痛だったのだ。
また、私の置かれた状況も心配していた。
この時にA氏に確認したのは、捜査一課はこの逮捕状のことをいつから知っていたのか、
ということだった。
警視庁が主管課として、一度も報告を受けないまま逮捕の日を迎えるようなことがあり得るのか?
そんな事は、特にこの件ではあり得なかった。なぜなら、以前はっきりとA氏から、
当初から本部(警視庁捜査一課)に報告している、と聞いていたからだ。
山口氏のような社会的地位のある人が関わる事件は、所轄だけで判断できないので、
一課には報告済みで、逮捕状を取ったことについても同様に報告が上がっていたはずだ。
そして、A氏が逐一相談していたM検事は、検事の中でもトップに値するくらい
経験もある人なので間違いはない、と聞いていたのだ。
逮捕が見送られた結果、被疑者と同じ敷地内で仕事をしなければならなくなった被害者としては、
当然聞く権利があるだろう。
やはりA氏は、今回は逮捕状を取るまでの間、高輪署の幹部を通じて、
署内で「本部」と呼ばれる警視庁の捜査一課に逐一報告を上げている、と言った。
もちろん、逮捕状を申請する段階でも。
「有名人だから逃走しない」という理由で逮捕を取り止めるなら、
その段階でいくらでもストップできたはずだ。
ということは、捜査一課の説明は正くない。
やはり、あの日A氏が「警視庁のトップです」と言った通り、
捜査一課よりももっと上のポストから、逮捕当日、
急にストップがかかったと考えるべきだった。
しかし、誰がストップをかけたのかを暴くのは、簡単なことではなかった。
この時は、それができるとは思っていなかった。』
義理堅いというか、律儀というか……。詩織さんの立場からしても、
例え弁解に近い内容だとしても何事もなかったかのように
そのまま放置されるよりはよっぽどよかったことだろう。
また他にも、弁護士の先生方、他のジャーナリストの方、
そういった方達の存在も詩織さんにとっては、
有り難かったに違いない。
『 翌日、知人のジャーナリストからも連絡があった。
「政府サイドが各メディアに対し、あれは筋の悪いネタだから触れないようが良いなどと、
報道自粛を勧めている。
各社がもともと及び腰なのは想像がつくが、これでは会見を報道する社があるかどうか……。
でも、会見はやるべきで、ただ、工夫が必要ですね。
しかし、なぜ政府サイドがここまで本件に介入する必要があるのか、不可解」
矢継ぎ早の連絡に、気持ちが混乱した。
そんな時、「週刊新潮」の記者に、メディアに対して私の会見に関する報道自粛を求める動きが、
水面下で拡がっているらしいと話すと、彼は軽い調子で、
「ああ、知ってますよ」
と言った。「だから何?」というようなその姿勢に、私はとても勇気づけられた。』
この「週刊新潮」の記者の方の毅然とした態度は、第三者から見ても頼もしいと思った。
このように忖度とは全く無縁なメディアも日本にはある。有り難いことだ。詩織さんのもとには、
今後もこういっった支援者達が集まってくることだろう。この本は出版して正解だったと思う。
一人でも多くの人に読んでもらいたい本だ。
『 私にはまだ話せる口があり、この写真の前に立てる体がある。
だから、このままで終わらせては絶対にいけない。
私自身が声を挙げよう。それしか道はないのだ。伝えることが仕事なのだ。
沈黙しては、この犯罪を容認してしまうことになる。』
伊藤 詩織